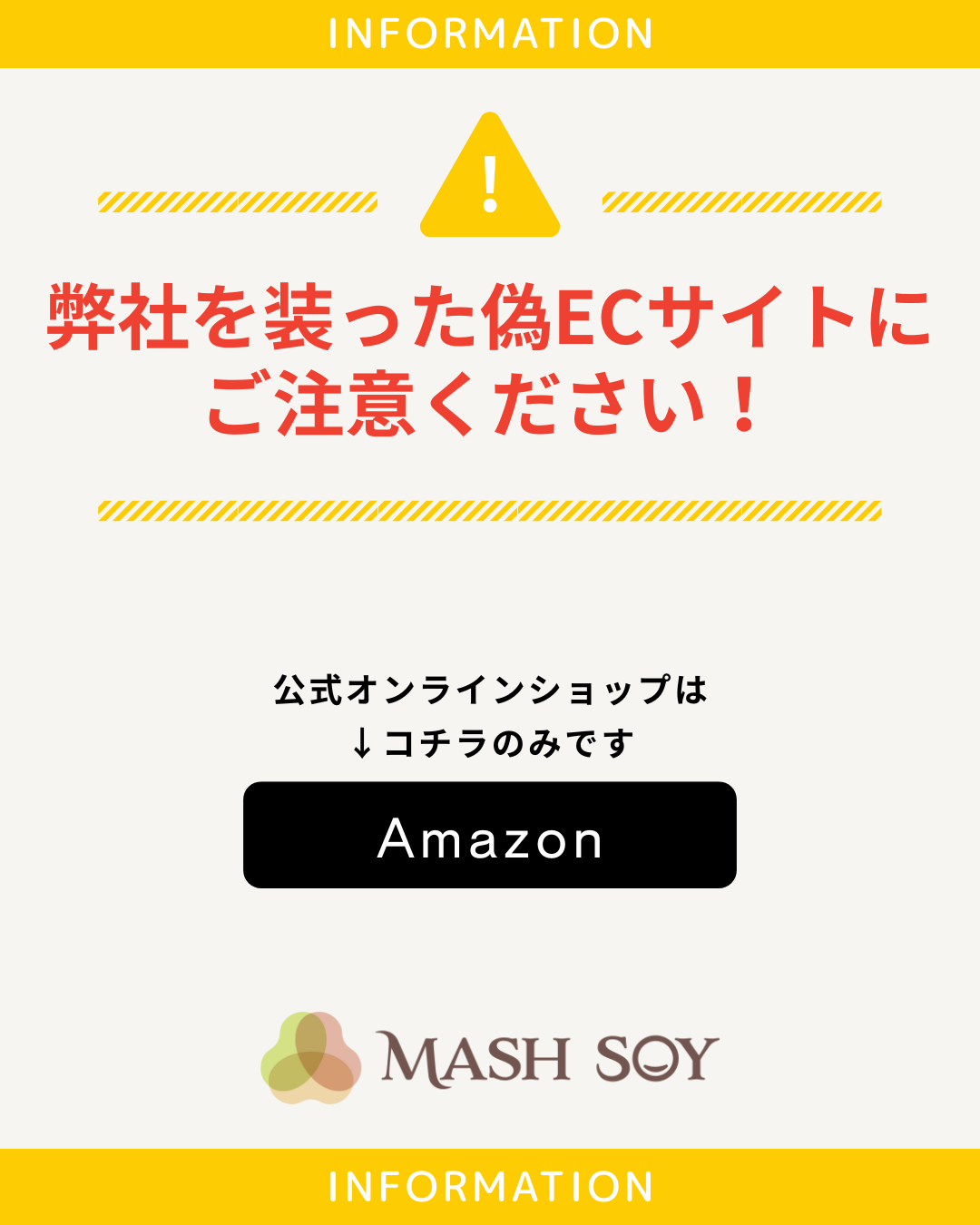食品添加物は、食の安全や利便性を支える一方で、健康への影響を懸念する声も多いテーマです。本記事では、食品添加物の役割や安全性に関する正しい知識を解説し、不安を軽減するための情報を提供します。
目次
食品添加物とは?その基本を知る
食品添加物の定義と種類
食品添加物とは、食品の製造や加工、保存、品質向上のために添加される物質を指します。日本では、食品衛生法で明確に定義されており、「食品の製造過程または加工や保存の目的で使用されるもの」とされています。
食品添加物は以下のように4つの種類に分類されています。
・指定添加物:厚生労働大臣が安全性を確認し、使用を認めた添加物(例:保存料、甘味料)
・既存添加物:長い使用経験があり、安全性が確保されているもの(例:にがり、寒天)
・天然香料:植物や動物由来の香料成分(例:バニラエッセンス、メントール)
・一般飲食物添加物:通常の食品として使用されるが、添加物としても利用されるもの(例:酢、塩)
これらの添加物は、それぞれ厳格な基準に基づいて使用されています。また、食品添加物には以下のような役割があります。
【食品添加物の主な役割】
| 役割 | 具体例 |
|---|---|
| 保存性の向上 | 保存料(食品の腐敗を防ぐ) |
| 見た目の改善 | 着色料(色鮮やかにする) |
| 風味の向上 | 調味料(甘みや旨味を加える) |
| 食感の改良 | 安定剤、ゲル化剤(滑らかさや弾力を作る) |
食品添加物の歴史と進化
食品添加物の歴史は古く、人類が食材を保存し始めた時代にまで遡ります。例えば、肉や魚の塩漬けや干物、燻製などの保存方法は、食品添加物の起源といえるでしょう。日本では、飛鳥時代にはすでに食品添加物が使用されていた記録があります。
例えば、くちなしの実から抽出した色素が食品の着色に使われています。また、豆腐を固めるための「にがり」や、中華麺に使われる「かんすい」も、古くから使用されてきた天然由来の食品添加物です。20世紀に入ると、食品の大量生産や長距離輸送が一般化し、それに伴い、化学的に合成された添加物が開発されました。これにより、食品の保存性や品質が飛躍的に向上しました。
一方で、食品添加物に対する不安や誤解も広がるようになりました。現在では、食品添加物の安全性が科学的に評価され、厳格な基準に基づいて管理されています。
例えば、日本では厚生労働省が食品添加物の規格や使用基準を定め、これに基づいて添加物が使用されています。また、国際的には、WHO(世界保健機関)やFAO(国連食糧農業機関)が設置したJECFA(合同食品添加物専門家会議)によって安全性が評価されています。このように、食品添加物は人類の知恵と科学技術の進化の中で開発され、私たちの食生活を豊かにするために役立っています。しかし、同時に適切な使用や正しい理解が必要です。
食品添加物の安全性はどう確保されている?
安全基準と規制の仕組み
食品添加物の安全性は、科学的な検証を経て厳格に管理されています。日本では、食品添加物を使用する際に「食品衛生法」が適用され、その基準が厚生労働省によって定められています。安全基準を設定するために、まず「無毒性量(No Observed Adverse Effect Level、 NOAEL)」が測定されます。これは動物実験を通じて、健康に影響を及ぼさない最大摂取量を確認するものです。この無毒性量の1/100を「一日摂取許容量(Acceptable Daily Intake、 ADI)」として、人間が毎日摂取しても安全とされる量が決められます。以下はADIの計算の仕組みを示したものです。
【ADI計算の概要】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 無毒性量(NOAEL) | 実験で確認された安全な最大量 |
| 安全係数(通常1/100) | 動物と人間の個体差を考慮した係数 |
| ADI | 安全係数を掛けて算出された安全量 |
誤解されがちな食品添加物のリスク
食品添加物は、科学的に安全と評価されているものだけが使用を許可されています。しかし、一部の誤解や偏見により、食品添加物全般に対して不安を抱く人が多いのも事実です。よくある誤解の1つは、食品添加物は「人工的なものは全て危険」という考え方です。しかし、天然由来の成分であっても過剰摂取すれば健康に害を及ぼす可能性があります。
例えば、塩や砂糖といった日常的な食品も、過剰摂取すると健康に悪影響を与えることが知られています。もう1つの誤解は、「無添加食品は安全で身体に良い」という考え方です。実際には、無添加表示の食品が安全性や健康効果を保証しているわけではありません。一部の無添加食品は保存性が低いため、適切に管理されないと食中毒のリスクが高まる可能性があります。
以下は食品添加物に関する誤解と事実をまとめた表です。
【食品添加物に関する誤解と事実】
| 誤解 | 事実 |
|---|---|
| 人工添加物は全て危険 | 科学的に安全性が確認されているもののみ使用可能 |
| 無添加食品は安全で健康に良い | 無添加表示は安全性や健康効果を保証するものではない |
| 全ての食品添加物が化学物質 | 天然由来の食品添加物も存在する(例:くちなし色素) |
例えば、かつて使用されていたアカネ色素は、新たな試験結果をもとに禁止されました。このように、食品添加物の安全性は最新の科学技術に基づき、厳密に管理されています。誤解を解消するためには、正しい知識を持ち、情報の信頼性を見極める力が重要です。
「無添加」が本当に安全なのか?
無添加表示の正しい見方
「無添加」とは、特定の食品添加物を使用していないことを意味します。しかし、この表現は必ずしも「完全に添加物が含まれていない」ことや「安全性が高い」ことを示しているわけではありません。
無添加表示には以下のような種類があります。
・一部無添加:保存料や着色料など、特定の食品添加物が使用されていない場合。
・全無添加:全ての食品添加物が不使用の場合(ただし非常に稀)。
また、消費者庁は2022年に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定しました。このガイドラインでは、以下のような表示が禁止されています。
【無添加表示に関する禁止事項】
| 表示例 | 理由 |
|---|---|
| 「完全無添加」 | 他の食品添加物が使用されている可能性があるため不正確 |
| 「無添加=健康に良い」 | 科学的根拠がないため誤解を招く可能性がある |
| 「化学調味料不使用(だし使用)」 | 化学調味料以外の食品添加物で同じ機能が補われている場合、不適切 |
このため、表示の詳細を確認することが大切です。
【無添加表示を見る際のポイント】
1.「何が無添加なのか」を確認する。
2.無添加の代替成分が使用されていないかをチェック。
3.保存方法や賞味期限を確認し、適切に管理されているかを確認する。
無添加信仰による選択ミスを防ぐ方法
「無添加=安全」という思い込みは、食品選びにおける誤解を生みやすい考え方です。特に、無添加食品を過信することで健康リスクが高まるケースもあります。
無添加信仰による典型的な選択ミスとして、以下のような事例があります。
・保存料不使用食品を適切に管理せず、食中毒を引き起こす。
・化学調味料不使用だが、過剰な塩分や砂糖が含まれる食品を選んでしまう。
・無添加食品と表示された商品が、別の添加物で代替されていることに気付かない。
これを防ぐためには、科学的な知識を持ち、適切な判断を行うことが重要です。
【無添加信仰を防ぐためのポイント】
1.表示内容を細かく確認する
・「無添加」としても別の添加物が含まれる場合があるため、成分表をチェックする。
2.食品の保存方法や賞味期限を理解する
・保存料不使用の場合、冷蔵保存が必須であるなど管理が必要なケースが多い。
3.無添加以外の要素も考慮する
・塩分や糖分などの栄養成分も確認し、健康バランスを重視する。
4.信頼できる情報源からの知識を得る
・科学的な根拠に基づいた情報を入手し、無添加食品の選び方を理解する。
無添加食品は適切に利用すれば健康的な選択肢の1つになります。ただし、「無添加」という言葉だけで安心せず、全体的な品質や成分を確認することが必要です。
まとめ|健康的な食生活に「MASH SOY」を取り入れよう
中でも、完全無添加で手軽に大豆の栄養を摂取できる「MASH SOY」は、現代の多忙なライフスタイルにぴったりの食品です。北海道産の丸大豆とおいしい水だけで作られたシンプルな素材だからこそ、安心して日々の食事に取り入れることができます。
また、「MASH SOY」はそのまま食べるのはもちろん、料理のアクセントとしても活用できる多彩な使い方が魅力です。栄養豊富で口当たりも良いペースト状の大豆食品なので、子どもから大人まで幅広い世代に支持されています。健康的な食生活を目指すためには、毎日の食事に無理なく続けられるアイテムを選ぶことがポイントです。
「MASH SOY」を活用して、家族みんなで楽しめるヘルシーな食卓を作りましょう。ぜひ一度、MASH SOYを試してみてください。
詳しくはMASH SOY公式サイトをご覧いただき、健康的で豊かな食生活をスタートさせてみてはいかがでしょうか?

Riko Kobayashi
小林 理子
略歴
2014年短期大学部家政科食物栄養専攻卒業 栄養士資格取得
2014年給食委託会社入社
2015年公立小学校の栄養士へ転職
2017年管理栄養士国家資格取得/フリーランス管理栄養士へWebライター、セミナー講師、食事指導、レシピ開発等で活躍
2019年オランダへ渡航(活動休止)
2023年フューチャーフーズ株式会社に入職
2024年フリーランス管理栄養士として活動再開
活動実績
高齢者施設、学校、保育園などでの給食提供を経験し、実務を通じて専門性を磨いた後、独学で管理栄養士国家試験に合格。以降はフリーランスとして、食事指導・セミナー登壇・レシピ開発・Webライターなど幅広い分野で活躍。
オランダ滞在中に妊娠・出産を経験し、日本帰国後は 大豆製品を使ったレシピ開発 や 食品臨床試験の食事調査 を行い、現在は再びフリーランスとして活動中。