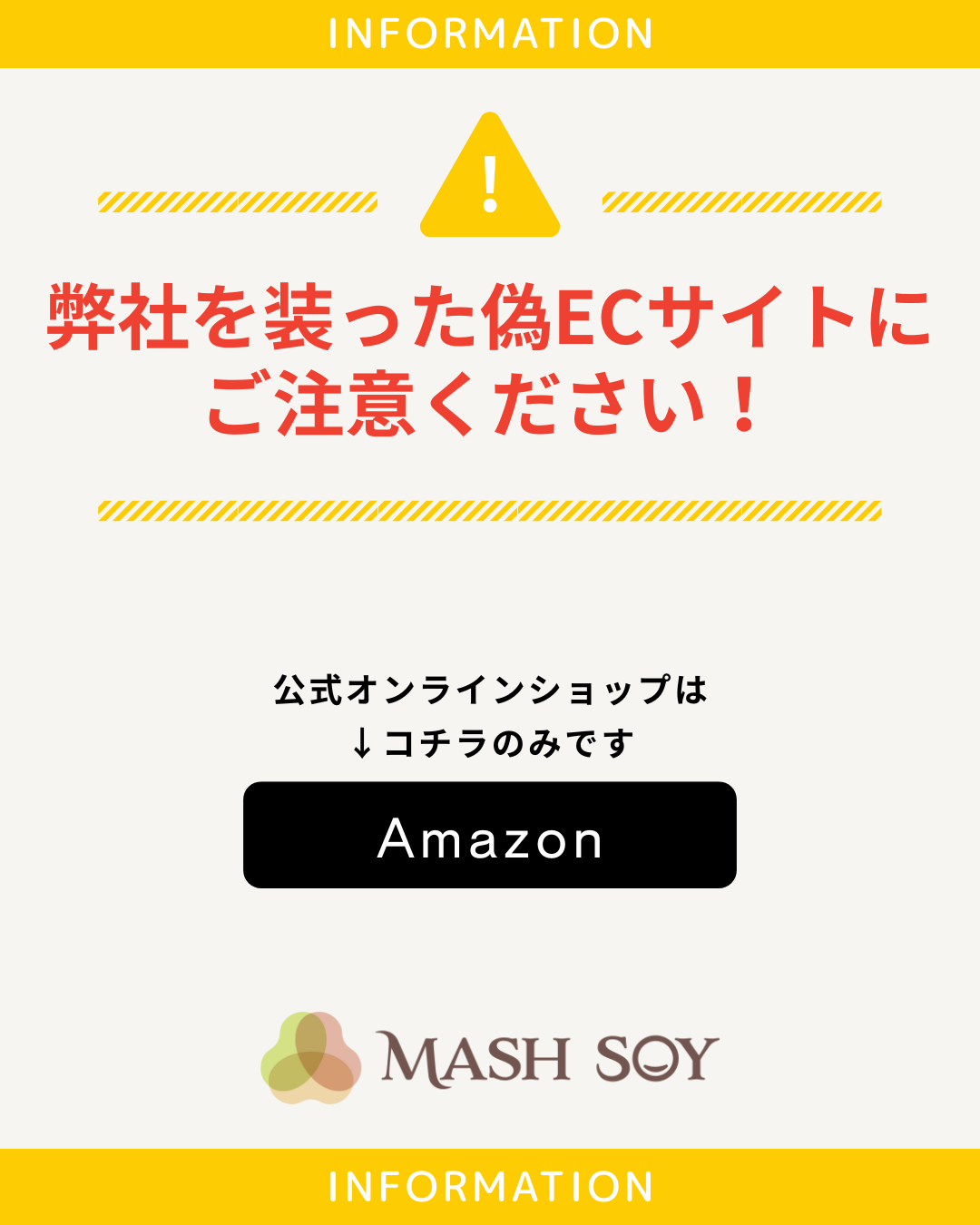食品添加物は私たちの日常生活に欠かせない存在ですが、「身体に悪い」というイメージも根強くあります。本記事では、食品添加物の定義や役割、安全性について簡単に解説し、正しい理解をサポートします。
目次
食品添加物の基本知識
食品添加物の定義とは
食品添加物は、日本の食品衛生法で明確に定義されています。食品衛生法第4条では、食品添加物を「食品の製造過程や加工、保存の目的で食品に添加、混和、浸潤その他の方法で使用する物」としています。簡単に言えば、食品の品質を保つため、または風味や見た目を向上させるために加えられる成分を指します。例えば、保存料は食品を腐らせないために重要な役割を果たします。
また、着色料は食品の見た目を鮮やかにし、甘味料は少量で甘みを増す効果があります。これらの成分は、日々の食生活において欠かせない存在です。
食品添加物には、以下のような分類があります。
【食品添加物の主な分類】
1.指定添加物: 厚生労働省が安全性を評価し、使用を許可した物質(例:キシリトール、ソルビン酸)
2.既存添加物: 長年使用され、安全性が確認されている天然由来の物質(例:クチナシ色素)
3.天然香料: 自然から採取された香り成分(例:バニラ香料)。
4.一般飲食物添加物: 通常食品として使用される成分を添加物として利用(例:寒天、食用油)
食品添加物の定義と分類を理解することで、その役割の重要性に気付くことができます。これらは安全性が確認された上で使用されているため、過度に恐れる必要はありません。
食品添加物が使われる理由
食品添加物が使用される背景には、現代の多様化した食生活を支えるための重要な理由があります。
1つ目は、食品の保存性を高めることです。
現代では、食品の流通や保存期間が長期化しています。そのため、保存料や酸化防止剤などを活用して、食品の腐敗を防ぎ、新鮮な状態を保つ必要があります。これにより、消費者は安心して食品を購入できます。
2つ目は、食品の味や見た目を向上させることです。
例えば、ハムやソーセージには発色剤が使われ、その鮮やかな色が消費者の購買意欲を高めます。また、香料や調味料は、食品に独特の香りや味わいを加え、食事を楽しむ要素を提供します。
3つ目は、食品の製造・加工を円滑にすることです。
例えば、ゼリーやプリンにはゲル化剤が使われ、特有の食感を生み出します。また、豆腐の製造では凝固剤が欠かせません。これらの添加物は、食品製造のプロセスを支えています。
4つ目として、栄養価を補強する目的が挙げられます。
ビタミンやミネラルを添加することで、栄養バランスを整える食品が増えています。特に子ども向けや高齢者向けの食品には、このような添加物が積極的に活用されています。
【食品添加物が使用される主な目的】
・保存性の向上: 食品を長持ちさせる(例:保存料、酸化防止剤)
・見た目や味の向上: 食品を美味しそうに見せる(例:着色料、香料、甘味料)
・製造効率の改善: 食品加工をスムーズに行う(例:膨張剤、乳化剤)
・栄養価の補強: 食事の不足を補う(例:ビタミン、カルシウム)
食品添加物の活用がなければ、私たちの食生活は非常に不便なものになってしまいます。 日持ちしない食品ばかりになり、物流や消費に大きな制限が生じるでしょう。
食品添加物の役割
食品添加物は、私たちの食生活を支える重要な要素の1つです。適切に使用されることで、食品の品質や安全性を向上させるだけでなく、日常の食事をより豊かにしてくれます。ここでは、食品添加物の具体的な役割とその使用例について詳しく解説します。
食品添加物が果たす4つの役割
食品添加物には、さまざまな目的と役割があります。それらは大きく分けて4つのカテゴリーに分類され、それぞれが重要な機能を果たしています。
1.食品の品質を保持する
食品添加物は、腐敗や変質を防ぐことで、食品の安全性を高めます。保存料や防カビ剤などは、微生物の繁殖を抑え、食品が長期間安全に食べられるようにするために使用されます。例えば、パンに添加される防カビ剤は、カビの発生を抑え、食品廃棄を減らす役割を果たします。
2.嗜好性を向上させる
味や香り、見た目を良くするためにも食品添加物は欠かせません。甘味料や香料、着色料は、食品の味や香りを引き立て、よりおいしく見えるようにします。例えば、発色剤を使ったハムは鮮やかな色を保ち、見た目から食欲をそそります。
3.製造・加工の効率を高める
食品添加物は、食品製造や加工の過程でも重要な役割を果たします。凝固剤や乳化剤などは、豆腐やアイスクリームなどの食品を作る際に必要不可欠です。これにより、スムーズな生産が可能となり、コストを抑えつつ高品質な製品が提供されます。
4.栄養価を補強・強化する
加工や調理の過程で失われた栄養素を補うために、食品添加物が使用されることがあります。ビタミン類やミネラルは、栄養価の向上や健康増進を目的として添加されます。例えば、カルシウム強化ミルクは、成長期の子どもや骨密度が気になる高齢者にとって大変役立つ製品です。
具体的な使用例
食品添加物は、私たちが日常的に消費するさまざまな食品に使われています。
以下に、その具体例を挙げてみましょう。
【食品添加物の具体的な使用例】
| 役割 | 食品 | 添加物の種類 |
|---|---|---|
| 保存性の向上 | パン、漬物 | 防カビ剤、保存料 |
| 見た目や味の向上 | ハム、ソーセージ | 発色剤、着色料 |
| 食品加工のサポート | 豆腐、ゼリー | 凝固剤、ゲル化剤 |
| 栄養価の補強 | 強化ミルク、栄養飲料 | ビタミン、ミネラル類 |
また、ゼリーにはゲル化剤が使われ、滑らかな食感が実現されています。さらに、甘味料や酸味料は、飲み物やお菓子の味を調えるために活用されています。これにより、食品がおいしさだけでなく、健康面でも価値を持つ商品として提供されています。
食品添加物は、一見すると目立たない存在ですが、食品の品質や安全性を支え、嗜好性や栄養価を向上させるために欠かせないものです。私たちが日々口にする食品の裏側には、これらの添加物が大きな役割を果たしています。
食品添加物の安全性と注意点
食品添加物は、現代の食生活において欠かせない存在ですが、安全性に関する疑問や不安を持つ方も少なくありません。また、「無添加食品」が注目される中で、誤解や偏ったイメージも広がっています。ここでは、食品添加物の安全性についての事実と、「無添加」という言葉に関する誤解を解説します。
食品添加物は安全?
食品添加物は、安全性を厳しく評価されたうえで使用が認められています。しかし、そのプロセスや基準について知る機会が少ないため、不安を感じる方が多いのも事実です。食品添加物の安全性は、科学的根拠に基づいて評価されています。
まず、各種試験によって、添加物が人体に及ぼす影響を調べます。その中で、動物実験を通じて何の悪影響も見られない最大量を「無毒性量」として設定します。この無毒性量の1/100以下の量を「一日摂取許容量(ADI)」として、人間が一生涯毎日摂取しても問題がない量と定めています。
また、日本では食品安全委員会が安全性のリスク評価を行い、厚生労働省が基準を策定しています。日本の基準は世界的に見ても非常に厳格であり、国際基準(JECFA)の安全基準にも準じています。
【食品添加物の安全性評価のプロセス】
| 評価段階 | 具体的内容 |
|---|---|
| 動物試験 | 毒性が現れない最大量(無毒性量)を決定 |
| 一日摂取許容量(ADI)の設定 | 無毒性量の1/100以下を安全量として設定 |
| 国際基準の策定 | FAOやWHOが基準を定め、各国が基準を整備 |
| 日本国内での基準化 | 厚生労働省が使用量や対象食品ごとに厳密な基準を制定 |
無添加食品の誤解
近年、「無添加」と記載された食品が注目されています。健康志向の高まりを背景に、多くの方が「無添加=安全」と考える傾向があります。しかし、無添加食品に関する理解には注意が必要です。まず、「無添加」とは、特定の食品添加物が使用されていないことを意味します。これがすべての添加物が不使用であるわけではない点に注意が必要です。
例えば、「保存料無添加」と記載されていても、保存料以外の添加物が使用されているケースがあります。消費者にとって重要なのは、何が無添加なのかを正確に理解することです。また、無添加食品が必ずしも安全で健康的であるとは限りません。
食品添加物は適切に使用されることで食品の安全性を保つ役割を果たしており、保存料がないことで食品が腐敗しやすくなる場合もあります。これにより、食品ロスや健康リスクが増加する可能性があります。
【無添加食品の注意点】
| 誤解されやすい点 | 実際の意味 |
|---|---|
| 無添加=全ての添加物が不使用 | 特定の添加物が不使用であるだけの場合が多い |
| 無添加=健康に良い | 保存料不使用のため腐敗しやすい食品もある |
| 無添加食品は添加物を含む食品より安全 | 添加物を適切に使用した食品の方が保存性や安全性が高い場合もある |
まとめ|食品添加物との適切な付き合い方と無添加食品の選び方
一方で、「無添加食品」への注目が高まる中、無添加表示が何を意味するのかを理解し、正しい情報に基づいて選ぶことが求められます。無添加食品は必ずしも健康的というわけではなく、保存性や利便性といった面でのデメリットも考慮する必要があります。
無添加食品を日常に取り入れるなら、大豆食品「MASH SOY」がおすすめです。北海道産の丸大豆とおいしい水のみを使用し、添加物を一切使用していないMASH SOYは、大豆の栄養素を手軽に摂取できる画期的な食品です。日々の食事に取り入れることで、健康的でバランスの取れた食生活を実現できます。
【MASH SOYのポイント】
・大豆イソフラボンや植物性たんぱく質など豊富な栄養素を含む
・青臭さやえぐみを抑えた優しい風味と口溶けの良さ
・さまざまな料理に活用できる便利さ
健康や美容に気を使いたい方、無添加食品を積極的に選びたい方にとって、MASH SOYは理想的な選択肢です。毎日の食事にMASH SOYを取り入れて、安心でおいしい食生活を楽しみましょう。
MASH SOYの詳細や購入方法については、公式オンラインショップをご覧ください。

Riko Kobayashi
小林 理子
略歴
2014年短期大学部家政科食物栄養専攻卒業 栄養士資格取得
2014年給食委託会社入社
2015年公立小学校の栄養士へ転職
2017年管理栄養士国家資格取得/フリーランス管理栄養士へWebライター、セミナー講師、食事指導、レシピ開発等で活躍
2019年オランダへ渡航(活動休止)
2023年フューチャーフーズ株式会社に入職
2024年フリーランス管理栄養士として活動再開
活動実績
高齢者施設、学校、保育園などでの給食提供を経験し、実務を通じて専門性を磨いた後、独学で管理栄養士国家試験に合格。以降はフリーランスとして、食事指導・セミナー登壇・レシピ開発・Webライターなど幅広い分野で活躍。
オランダ滞在中に妊娠・出産を経験し、日本帰国後は 大豆製品を使ったレシピ開発 や 食品臨床試験の食事調査 を行い、現在は再びフリーランスとして活動中。