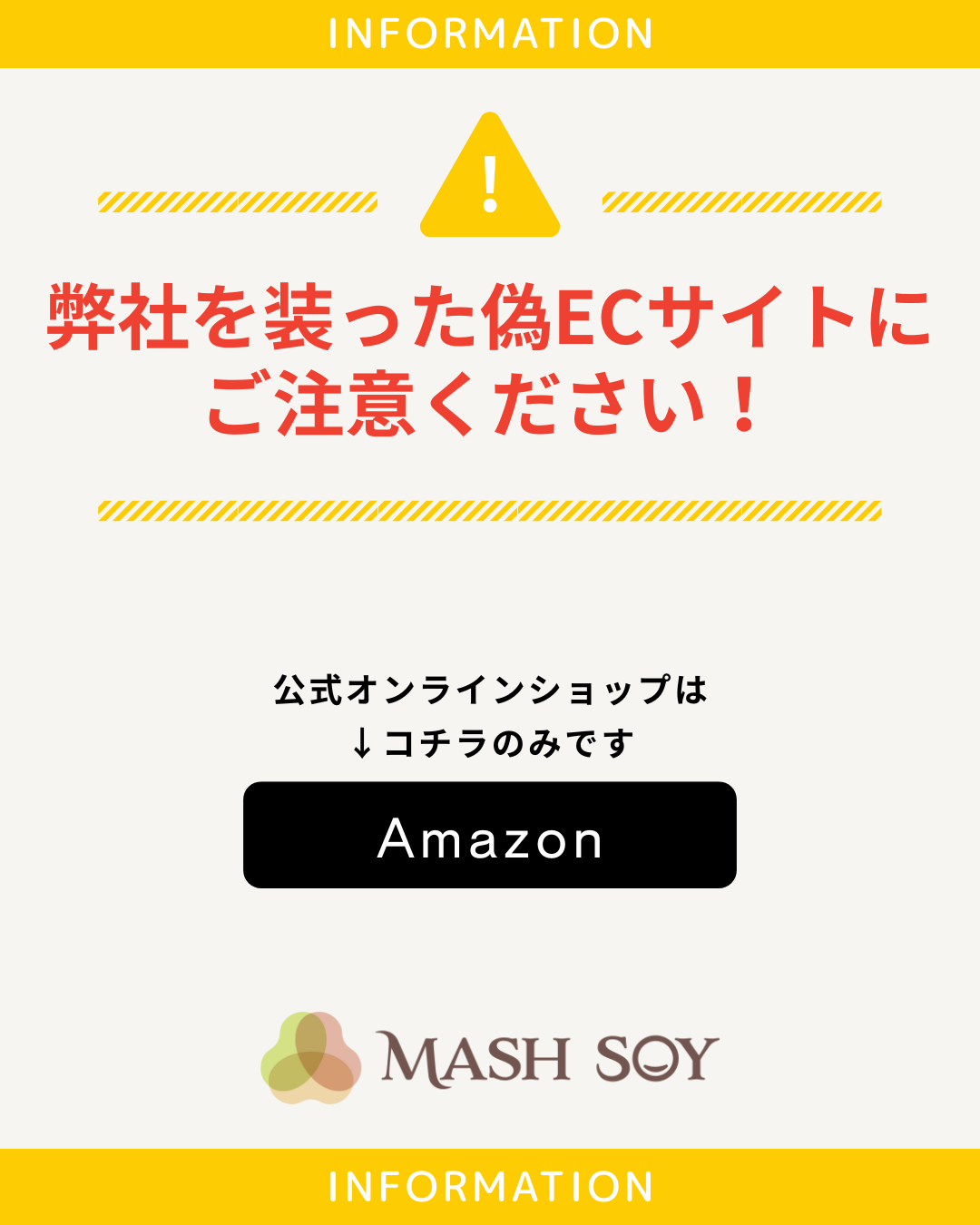納豆は栄養価が高く、日本のスーパーフードとも言われる発酵食品です。しかし、健康に良いからといって食べ過ぎると、思わぬ健康リスクを招くことも。本記事では、納豆の適量や食べ過ぎによるデメリット、バランスの良い食べ方について詳しく解説します。
目次
納豆の栄養と健康効果
納豆は、発酵食品の中でも特に栄養価が高く、健康に良い食品として知られています。その秘密は、大豆由来の栄養素に加え、発酵によって生み出される成分が豊富に含まれている点にあります。納豆を日常的に食べることで、さまざまな健康効果が期待できます。本章では、納豆に含まれる主な栄養素と、それがもたらす健康効果について詳しく解説します。
納豆に含まれる主な栄養素
納豆は、たんぱく質やビタミン、ミネラルが豊富な食品です。さらに、発酵によって特有の成分が加わることで、健康への影響がより強くなります。以下の表に、納豆に含まれる主な栄養素とその働きをまとめました。
| 栄養素 | 期待できる効果 |
|---|---|
| たんぱく質 | 筋肉の維持・修復、エネルギー代謝の促進 |
| 食物繊維 | 腸内環境の改善、便秘予防 |
| ビタミンK | 骨の健康維持、血液凝固のサポート |
| 大豆イソフラボン | ホルモンバランスの調整、更年期症状の緩和 |
| ナットウキナーゼ | 血栓の予防、血液サラサラ効果 |
| ミネラル(鉄・マグネシウム・カリウム) | 貧血予防、血圧調整、ストレス軽減 |
特に、納豆ならではの成分としてナットウキナーゼが挙げられます。これは、納豆菌による発酵で生まれる酵素であり、血液をサラサラにし、血栓を予防する効果が期待されています。また、ビタミンKの含有量は食品の中でもトップクラスで、カルシウムの吸収を助け、骨を丈夫にする働きがあります。
納豆がもたらす健康効果
納豆に含まれる栄養素は、さまざまな健康効果をもたらします。日常的に納豆を取り入れることで、以下のようなメリットが期待できます。
1. 腸内環境の改善
納豆に含まれる食物繊維や納豆菌は、腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整えます。これにより、便秘の改善や免疫力の向上が期待できます。
2. 血液をサラサラにする
ナットウキナーゼは、血液を固まりにくくする働きがあり、動脈硬化や心筋梗塞の予防に役立つと言われています。また、血流を促進することで、冷え性の改善にもつながります。
3. 骨を丈夫にする
ビタミンKは、カルシウムが骨に定着するのを助ける働きがあります。そのため、骨粗しょう症の予防や、骨折リスクの低減が期待できます。
4. ホルモンバランスを整える
大豆イソフラボンは、女性ホルモン「エストロゲン」と似た働きをするため、更年期症状の軽減や、美肌効果が期待できます。また、男性にとっても、ホルモンバランスを整える効果があるとされています。
5. 免疫力の向上
納豆菌が腸内環境を整えることで、身体全体の免疫機能が向上します。風邪やインフルエンザの予防にも役立ち、健康維持に貢献する食品と言えるでしょう。
納豆の食べ過ぎが引き起こすリスク
納豆は健康に良い発酵食品ですが、過剰に摂取すると健康への悪影響を及ぼす可能性があります。特に、大豆由来の成分や発酵によって生じる栄養素には、一定の摂取制限が必要なものもあります。本章では、納豆の食べ過ぎによるリスクについて、大豆イソフラボン・プリン体・ビタミンKの3つの観点から詳しく解説します。
大豆イソフラボンの過剰摂取による影響
納豆には、大豆由来の大豆イソフラボンが豊富に含まれています。この成分は、女性ホルモン「エストロゲン」と似た働きを持つため、更年期障害の軽減や骨密度の維持に効果的と言われています。しかし、過剰に摂取すると以下のような影響を及ぼす可能性があります。
1. ホルモンバランスの乱れ
大豆イソフラボンを過剰に摂取すると、体内のホルモンバランスが崩れることがあります。特に、女性ホルモンの影響を受けやすい方は、生理不順やPMS(生理前症候群)の悪化を招くことがあります。
2. 乳がんリスクの増加
大豆イソフラボンは適量であれば乳がんの予防に役立つとされています。しかし、過剰に摂取すると、エストロゲンが過剰に分泌され、乳がんのリスクを高める可能性が指摘されています。
3. 甲状腺機能の低下
大豆イソフラボンは、甲状腺ホルモンの生成に影響を与えることが知られています。特に、ヨウ素不足の方が過剰摂取すると、甲状腺機能低下を引き起こす恐れがあります。
1日の適量目安
大豆イソフラボンの1日の摂取上限は70〜75mgとされています。納豆1パック(50g)には約35mgの大豆イソフラボンが含まれているため、1日2パックを超えないようにするのが適切です。
プリン体の過剰摂取と痛風リスク
納豆は、健康に良いたんぱく源ですが、プリン体が比較的多く含まれる食品でもあります。プリン体は体内で分解されると尿酸に変わり、尿酸値が高くなると痛風のリスクが増加します。
1. 痛風の発症リスク
痛風は、血中の尿酸濃度が高くなり、関節に尿酸結晶が蓄積することで発症します。特に、尿酸値が高めの方が納豆を食べ過ぎると、痛風の発症リスクが上がるため注意が必要です。
2. 尿酸値の上昇
納豆1パック(50g)には約57mgのプリン体が含まれています。日本痛風・尿酸核酸学会の推奨する1日のプリン体摂取量の上限は400mgのため、納豆を大量に食べると尿酸値が上昇する可能性があります。
1日の適量目安
痛風のリスクを避けるためには、1日1パック程度に抑えるのが理想的です。また、レバーや魚卵など他のプリン体が多い食品と併せて摂取しないように注意しましょう。
ビタミンKの過剰摂取と薬の影響
納豆にはビタミンKが豊富に含まれており、これは骨の健康維持や血液凝固に重要な役割を果たす栄養素です。しかし、特定の薬を服用している方にとっては注意が必要な成分でもあります。
1. 抗血栓薬(ワーファリン)との相互作用
血液をサラサラにする薬(ワーファリンなど)を服用している方は、納豆の摂取を控える必要があります。これは、ビタミンKが血液の凝固を促進する作用を持つため、薬の効果を打ち消してしまう可能性があるからです。
2. 血栓リスクの増加
ビタミンKを過剰に摂取すると、血液が必要以上に凝固しやすくなるため、血栓ができるリスクが高まることが考えられます。特に、動脈硬化や心血管系の疾患を持つ方は、ビタミンKの摂取量に注意が必要です。
1日の適量目安
健康な方の場合、ビタミンKの1日の摂取上限は特に設定されていませんが、納豆1パックで1日に必要な量を大きく超えてしまうことが多いため、1日1パックを目安にするのが適切です。
納豆の適量とバランスの良い食べ方 
納豆は健康に良い発酵食品として、多くの方に親しまれています。しかし、健康効果を得るためには適量を守ることが重要です。また、納豆だけに偏るのではなく、他の食材と組み合わせて栄養バランスを整えることも大切です。本章では、納豆の適量と、栄養バランスを考えた食べ方について詳しく解説します。
1日の適量はどのくらい?
納豆は栄養豊富な食品ですが、食べ過ぎると健康リスクを引き起こす可能性があります。適量を守りながら、日々の食事に取り入れることが重要です。
1. 大豆イソフラボンの観点からの適量
納豆には大豆イソフラボンが多く含まれています。大豆イソフラボンの1日の摂取上限は70〜75mgとされています。納豆1パック(50g)には約35mgの大豆イソフラボンが含まれているため、1日1〜2パックが適量と考えられます。
2. プリン体の観点からの適量
納豆にはプリン体が含まれており、過剰に摂取すると痛風リスクが上がる可能性があります。日本痛風・尿酸核酸学会では、1日のプリン体摂取量の上限を400mgとしています。納豆1パック(50g)には約57mgのプリン体が含まれているため、1日1パック程度に抑えるのが理想的です。
3. ビタミンKの観点からの適量
納豆はビタミンKが豊富な食品であり、血液凝固作用を持つため、抗血栓薬を服用中の方は特に注意が必要です。一般的には過剰摂取の心配は少ないものの、1日1パックを目安にするのが無難でしょう。
4. カロリーの観点からの適量
納豆は低カロリーなイメージがありますが、1パック(50g)で約100kcalあります。1日2パック以上食べると、意外とカロリー摂取量が増えてしまうため、適量を守ることが重要です。
納豆と相性の良い食材で栄養バランスを整える
納豆は栄養豊富ですが、それだけでは全ての栄養素をバランス良く摂ることはできません。他の食材と組み合わせることで、より健康的な食事にすることができます。
1. たんぱく質を補う食材
納豆には植物性たんぱく質が豊富ですが、動物性たんぱく質と組み合わせることで、よりバランスの取れた栄養摂取が可能です。
【おすすめの食材】
– 卵(納豆+卵=「納豆卵かけご飯」)
– 鶏ささみ(高たんぱく低脂質)
– 魚(サーモン・しらす)(オメガ3脂肪酸が豊富)
– 鶏ささみ(高たんぱく低脂質)
– 魚(サーモン・しらす)(オメガ3脂肪酸が豊富)
2. 食物繊維を補う食材
納豆には食物繊維が含まれていますが、さらに多く摂るためには野菜や海藻類をプラスするのがおすすめです。
【おすすめの食材】
– オクラ(ネバネバ成分で腸内環境を整える)
– 長いも(消化を助ける)
– わかめ・もずく(ミネラルも補給できる)
– 長いも(消化を助ける)
– わかめ・もずく(ミネラルも補給できる)
3. 発酵食品との組み合わせ
納豆は発酵食品なので、他の発酵食品と組み合わせることで、腸内環境をさらに整える効果が期待できます。
【おすすめの食材】
– ヨーグルト(乳酸菌と納豆菌の相乗効果)
– キムチ(発酵食品同士の組み合わせで整腸作用アップ)
– 味噌汁(発酵食品+温かい食事で消化を助ける)
– キムチ(発酵食品同士の組み合わせで整腸作用アップ)
– 味噌汁(発酵食品+温かい食事で消化を助ける)
4. カルシウムを補う食材
納豆には骨を強くするビタミンKが豊富ですが、カルシウムと組み合わせることで、より効果的に骨を強化できます。
【おすすめの食材】
– 牛乳・チーズ(カルシウム豊富)
– 小松菜・チンゲン菜(植物性カルシウム)
– しらす・桜えび(カルシウム+たんぱく質)
– 小松菜・チンゲン菜(植物性カルシウム)
– しらす・桜えび(カルシウム+たんぱく質)
まとめ|納豆を適量に食べて健康維持を目指そう 
納豆は栄養価が高く、腸内環境の改善や生活習慣病予防などさまざまな健康効果が期待できる食品です。しかし、過剰に摂取すると大豆イソフラボンの影響やプリン体の摂取過多による健康リスクが生じる可能性もあります。健康を維持するためには、1日1〜2パックを目安にし、バランスの良い食事に組み込むことが大切です。また、納豆だけに頼るのではなく、他の大豆製品も上手に取り入れることで、より多くの栄養素を効率よく摂取できます。特に、エクオールを体内で産生しやすい環境を整えるには、大豆イソフラボンを適切に摂ることが重要です。エクオールは、女性ホルモンの働きをサポートし、更年期症状の軽減や美肌効果が期待される成分ですが、腸内で産生できるかどうかは個人差があります。そのため、効率よく大豆イソフラボンを摂取できる食品の選択がポイントになります。
そんな方におすすめなのが、大豆の栄養を手軽に摂取できる「MASH SOY」です。MASH SOYは、北海道産の丸大豆とおいしい水だけで作られた無添加の大豆食品で、大豆イソフラボンをはじめとする栄養素を余すことなく摂取できます。また、ペースト状なので料理に取り入れやすく、スープやソース、スムージーなどさまざまなレシピに活用できるのも魅力です。
そんな方におすすめなのが、大豆の栄養を手軽に摂取できる「MASH SOY」です。MASH SOYは、北海道産の丸大豆とおいしい水だけで作られた無添加の大豆食品で、大豆イソフラボンをはじめとする栄養素を余すことなく摂取できます。また、ペースト状なので料理に取り入れやすく、スープやソース、スムージーなどさまざまなレシピに活用できるのも魅力です。
納豆を適量に食べながら、MASH SOYを活用してバランスよく大豆の栄養を取り入れることで、健康維持や美容、ホルモンバランスのサポートにつなげていきましょう。
あなたの健康と美容のために、納豆やMASH SOYを活用した食生活を始めてみませんか?

Riko Kobayashi
小林 理子
略歴
2014年短期大学部家政科食物栄養専攻卒業 栄養士資格取得
2014年給食委託会社入社
2015年公立小学校の栄養士へ転職
2017年管理栄養士国家資格取得/フリーランス管理栄養士へWebライター、セミナー講師、食事指導、レシピ開発等で活躍
2019年オランダへ渡航(活動休止)
2023年フューチャーフーズ株式会社に入職
2024年フリーランス管理栄養士として活動再開
活動実績
高齢者施設、学校、保育園などでの給食提供を経験し、実務を通じて専門性を磨いた後、独学で管理栄養士国家試験に合格。以降はフリーランスとして、食事指導・セミナー登壇・レシピ開発・Webライターなど幅広い分野で活躍。
オランダ滞在中に妊娠・出産を経験し、日本帰国後は 大豆製品を使ったレシピ開発 や 食品臨床試験の食事調査 を行い、現在は再びフリーランスとして活動中。
RECOMMEND