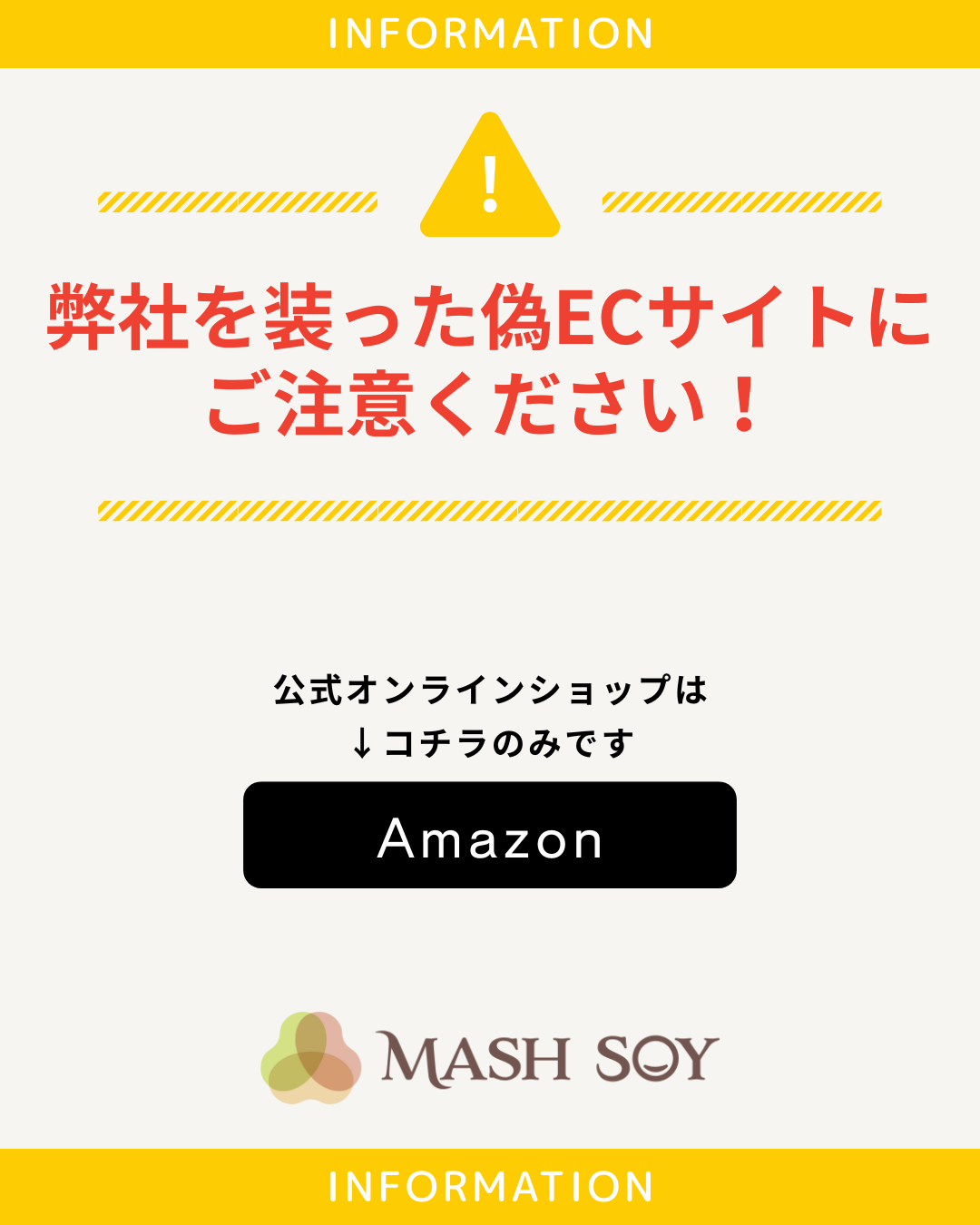納豆は栄養価が高く、離乳食に適した食材です。しかし、独特の粘りや風味があるため、赤ちゃんに与える際には工夫が必要です。本記事では、納豆を離乳食に取り入れる時期やメリット、調理方法、保存方法、そしておすすめレシピをご紹介します。
目次
離乳食で納豆を始める時期と適量
納豆は栄養価が高く、消化吸収に優れた食材であり、離乳食として取り入れるのに適しています。しかし、赤ちゃんの成長段階に応じて、適切な時期や量を見極めることが重要です。本章では、納豆を与え始める適切な時期と、月齢ごとの適量について詳しく解説します。
納豆を与え始める適切な時期
納豆は、離乳中期(生後7〜8ヶ月頃)から与えられる食材です。この時期はたんぱく質を摂取するための食材の幅を広げる段階であり、納豆のような発酵食品も取り入れやすくなります。ただし、最初に与える際は 「ひきわり納豆」を選ぶのがポイントです。ひきわり納豆は、通常の納豆より粒が細かく、皮が取り除かれているため消化しやすい特徴があります。納豆を初めて与える際の注意点は以下の通りです。
・少量から始める(最初は 小さじ1杯程度)
・加熱処理を行う(湯通しや電子レンジ加熱で、納豆の粘り気を軽減)
・単独で与える(アレルギー反応を確認しやすくするため)
・午前中に試す(万が一アレルギー症状が出た場合、すぐに受診できるようにする)
納豆は 大豆アレルギーの可能性がある食品なので、初めて与えるときは医療機関の診療時間内に試すと安心です。また、赤ちゃんの様子を見ながら、徐々に量を増やしていくことが大切です。
・少量から始める(最初は 小さじ1杯程度)
・加熱処理を行う(湯通しや電子レンジ加熱で、納豆の粘り気を軽減)
・単独で与える(アレルギー反応を確認しやすくするため)
・午前中に試す(万が一アレルギー症状が出た場合、すぐに受診できるようにする)
納豆は 大豆アレルギーの可能性がある食品なので、初めて与えるときは医療機関の診療時間内に試すと安心です。また、赤ちゃんの様子を見ながら、徐々に量を増やしていくことが大切です。
月齢別の納豆の適量
赤ちゃんの成長に合わせて、納豆の量や形状を調整することで、安全に取り入れられます。以下の表を参考に、月齢ごとに適した量や調理方法を確認しましょう。
| 月齢 | 目安量 | 形状・調理方法 |
|---|---|---|
| 離乳中期(7~8ヶ月) | 10~15g(小さじ1〜2) | ひきわり納豆をさらに細かく刻み、加熱して粘り気を取る |
| 離乳後期(9~11ヶ月) | 18g程度(大さじ1弱) | ひきわり納豆をそのまま使用、または刻む |
| 離乳完了期(1歳~1歳6ヶ月) | 20g程度(大さじ1強) | 粒納豆も可。軽く刻んで与える |
離乳中期(7~8ヶ月頃)
この時期の赤ちゃんは食材をすりつぶした状態で食べることが基本です。そのため、納豆も湯通しして粘り気を取り、細かく刻んで与えます。また、加熱することで風味がマイルドになり、赤ちゃんにとって食べやすくなります。
離乳後期(9~11ヶ月頃)
歯ぐきで食べ物をつぶすことができるようになるため、ひきわり納豆をそのまま与えてもOKです。粒納豆を使う場合は包丁で刻んで食べやすい大きさにすると安心です。納豆をおかゆや野菜と混ぜることで、より食べやすくなります。
離乳完了期(1歳~1歳6ヶ月頃)
この時期になると、赤ちゃんの咀嚼力が向上し粒納豆も食べられるようになります。ただし、喉に詰まるリスクがあるため、最初は粗く刻むなどして、食べやすい状態で提供しましょう。また、納豆の粘り気が苦手な場合は炒めたり焼いたりして調理すると、風味や食感が変わり食べやすくなります。
納豆を離乳食に取り入れるメリット
納豆は栄養価が高く、赤ちゃんの成長に必要な成分を豊富に含む食材です。また、発酵によって消化吸収が良くなるため、赤ちゃんの離乳食として適しています。本章では、納豆の栄養価と消化吸収の良さについて詳しく解説します。
栄養価の高さ
納豆は植物性たんぱく質を多く含み、離乳食に最適な食材の一つです。たんぱく質は筋肉や臓器の発達を助ける重要な栄養素であり、成長期の赤ちゃんにとって欠かせません。さらに、納豆には鉄分・カルシウム・ビタミンB群などの栄養素が豊富に含まれています。特に鉄分は、生後6ヶ月以降の赤ちゃんにとって不足しやすい栄養素の一つです。
| 栄養素 | 期待できる効果 |
|---|---|
| たんぱく質 | 筋肉・臓器・皮膚の成長をサポート |
| 鉄分 | 貧血予防・血液の生成を助ける |
| カルシウム | 骨や歯の形成を促進 |
| ビタミンB群 | エネルギー代謝を助け、疲労回復をサポート |
| 食物繊維 | 腸内環境を整え、便秘を予防 |
また、納豆に含まれるナットウキナーゼという酵素は、血液をサラサラにする効果があるとされ、大人にも良い影響をもたらします。赤ちゃんにとっては血流をスムーズにすることで、全身の成長をサポートする可能性があります。納豆は、他のたんぱく質源である豆腐や肉・魚に比べて調理が簡単であり、食べやすいのも魅力です。さらに、発酵によって大豆よりも栄養価が高まっているため、同じ大豆食品の中でも特に優れた栄養源と言えます。
消化吸収の良さ
赤ちゃんの消化機能は未発達であり、食材によっては消化に時間がかかることがあります。しかし、納豆は発酵食品であるため大豆よりも消化吸収が良く、赤ちゃんの胃腸に優しい食材です。納豆の発酵によって生まれるプロバイオティクス(善玉菌) は、腸内環境を整える働きを持っています。このため、納豆を食べることで便秘の予防や、消化を助ける効果が期待できます。さらに、納豆に含まれる酵素の働きによって、たんぱく質が分解され、吸収されやすい形になります。これにより、赤ちゃんの身体に必要な栄養素を効率よく摂取できるのが大きなメリットです。納豆を食べることで期待できる消化吸収のメリットは以下の通りです。
・発酵によってたんぱく質が分解され、消化しやすい
・腸内の善玉菌が増え、便秘の予防に役立つ
・胃腸に負担をかけにくく、消化器官の発達をサポートする
特に、離乳食初期から中期にかけては消化の良さが重要になります。そのため、納豆をうまく取り入れることで赤ちゃんの消化器官への負担を軽減し、スムーズな成長を助けることとなるでしょう。
・発酵によってたんぱく質が分解され、消化しやすい
・腸内の善玉菌が増え、便秘の予防に役立つ
・胃腸に負担をかけにくく、消化器官の発達をサポートする
特に、離乳食初期から中期にかけては消化の良さが重要になります。そのため、納豆をうまく取り入れることで赤ちゃんの消化器官への負担を軽減し、スムーズな成長を助けることとなるでしょう。
納豆の調理方法と保存方法
納豆は離乳食に適した食材ですが、赤ちゃんが食べやすいように適切な下処理や調理が必要です。また、保存方法を工夫すれば忙しい毎日の食事準備がスムーズになります。本章では、納豆の下処理や加熱方法、冷凍保存のコツについて詳しく解説します。
納豆の下処理と加熱方法
納豆は発酵食品であり、 独特の粘り気やにおいがあります。赤ちゃんが食べやすくするためには下処理を行い、必要に応じて加熱することが大切です。
下処理のポイント
赤ちゃんが食べやすい状態にするために、以下の下処理を行いましょう。
・納豆を湯通しして粘りを減らす
・ザルに納豆を入れ、熱湯を回しかける。
・粘りが気になる場合は、湯を2回ほどかけると軽減できる。
・ひきわり納豆を使うと手間が省ける
・皮が取り除かれているため、赤ちゃんが消化しやすく、食べやすい。
・粒納豆は細かく刻む
・大きい粒のままだと喉に詰まりやすいため、包丁で刻んでおくと安心。
・納豆を湯通しして粘りを減らす
・ザルに納豆を入れ、熱湯を回しかける。
・粘りが気になる場合は、湯を2回ほどかけると軽減できる。
・ひきわり納豆を使うと手間が省ける
・皮が取り除かれているため、赤ちゃんが消化しやすく、食べやすい。
・粒納豆は細かく刻む
・大きい粒のままだと喉に詰まりやすいため、包丁で刻んでおくと安心。
加熱方法の選択
納豆は加熱せずに食べることもできますが、 初めて与える際は加熱が推奨されています。加熱することで独特の風味が和らぎ、食べやすくなるため、赤ちゃんの好みに合わせて調整しましょう。
| 加熱方法 | 手順 | ポイント |
|---|---|---|
| 湯通し | ザルに納豆を入れ、熱湯を回しかける | 粘りが軽減し、食べやすくなる |
| 電子レンジ | 耐熱容器に納豆と大さじ1の水を入れ、ラップをかけ加熱(600Wで約20秒) | においが抑えられ、風味がまろやかになる |
| フライパン | 少量の水と一緒に弱火で炒める | 炒めることで香ばしさが増し、食感が変わる |
納豆の栄養素は加熱しても大きく損なわれないため、赤ちゃんの好みに応じた方法で調理するのがおすすめです。
納豆の冷凍保存方法
納豆は冷蔵では賞味期限が短いため、冷凍保存が便利です。小分けにして冷凍することで、 必要な分だけ解凍でき、離乳食の準備が楽になります。
冷凍保存の方法
納豆はパックのまま冷凍することも可能ですが、 赤ちゃん用に小分けにしておくと使いやすいです。
1. 納豆を小分けにする
・1回分(約10g〜15g)ずつラップで包む。
・製氷皿に小分けして凍らせ、凍ったら フリーザーバッグに移すとさらに便利。
・1回分(約10g〜15g)ずつラップで包む。
・製氷皿に小分けして凍らせ、凍ったら フリーザーバッグに移すとさらに便利。
2. 密閉して冷凍庫に入れる
・納豆は空気に触れると風味が落ちやすい ため、密閉できる容器やフリーザーバッグを活用する。
・保存期間は約1ヶ月が目安だが、できるだけ早めに使い切るのが理想。
・納豆は空気に触れると風味が落ちやすい ため、密閉できる容器やフリーザーバッグを活用する。
・保存期間は約1ヶ月が目安だが、できるだけ早めに使い切るのが理想。
3. 解凍方法を工夫する
・電子レンジで加熱(600Wで20〜30秒) するとすぐに使える。
・冷蔵庫で自然解凍すれば、温度変化が少なく風味を保ちやすい。
・熱湯をかけて解凍すると、粘りが抑えられ、食べやすくなる。
・電子レンジで加熱(600Wで20〜30秒) するとすぐに使える。
・冷蔵庫で自然解凍すれば、温度変化が少なく風味を保ちやすい。
・熱湯をかけて解凍すると、粘りが抑えられ、食べやすくなる。
冷凍保存のメリット
・一度にまとめて作り置きができるため、離乳食の準備が時短になる。
・小分けにすれば必要な分だけ使えるので、無駄が出にくい。
・長期間保存できるため、忙しい日でもすぐに栄養価の高い納豆を取り入れられる。
・小分けにすれば必要な分だけ使えるので、無駄が出にくい。
・長期間保存できるため、忙しい日でもすぐに栄養価の高い納豆を取り入れられる。
納豆が苦手な赤ちゃんへの対処法
納豆は栄養価が高く、腸内環境を整える発酵食品ですが、特有の粘りやにおいが苦手な赤ちゃんも少なくありません。無理に食べさせるのではなく、 工夫しながら徐々に慣れさせることが大切です。ここでは、納豆が苦手な赤ちゃんに食べやすくするための対処法をご紹介します。
他の食材との組み合わせ
納豆の粘りやにおいを和らげるには、他の食材と組み合わせるのが効果的です。野菜や炭水化物と混ぜることで、 風味がマイルドになり、食べやすくなります。
おすすめの組み合わせ食材
| 食材 | 特徴 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| ごはん・おかゆ | 風味をなじませやすく、粘りが減る | 口当たりが良くなり、においが気になりにくい |
| 豆腐 | 大豆食品同士で相性が良い | 口当たりがやわらかくなり、滑らかな食感になる |
| じゃがいも・さつまいも | 甘みがあり、食べやすい | ほんのり甘さをプラスし、納豆のクセを軽減 |
| ほうれん草・小松菜 | 栄養価が高く、緑黄色野菜との相性が良い | 彩りも良くなり、ビタミン補給にも役立つ |
| ひき肉・魚 | たんぱく質を補給でき、風味をプラスできる | 納豆の風味が抑えられ、より食べやすくなる |
組み合わせる際のポイント
・少量の納豆から始める
赤ちゃんの苦手意識を減らすため、 最初は少量からスタートしましょう。
赤ちゃんの苦手意識を減らすため、 最初は少量からスタートしましょう。
・食材をなめらかにする
例えば、おかゆや豆腐に混ぜると食感が滑らかになり、飲み込みやすくなります。
例えば、おかゆや豆腐に混ぜると食感が滑らかになり、飲み込みやすくなります。
・納豆のクセを抑える食材を選ぶ
じゃがいもやさつまいもなどの甘みがある食材と混ぜると、納豆のにおいを和らげられます。
じゃがいもやさつまいもなどの甘みがある食材と混ぜると、納豆のにおいを和らげられます。
調理方法の工夫
調理方法を変えることで、 食べやすさが大きく向上します。納豆の粘りやにおいを軽減しながら、赤ちゃんが受け入れやすい食感や風味に調整しましょう。
粘りやにおいを抑える方法
1. 湯通しする
・ザルに納豆を入れ、 熱湯を回しかけると粘りが減る。
・においも和らぐため、苦手な赤ちゃんにおすすめ。
・ザルに納豆を入れ、 熱湯を回しかけると粘りが減る。
・においも和らぐため、苦手な赤ちゃんにおすすめ。
2. 炒める
・少量の水と一緒にフライパンでさっと炒める。
・風味が変わり、納豆特有のクセが薄まる。
・少量の水と一緒にフライパンでさっと炒める。
・風味が変わり、納豆特有のクセが薄まる。
3. 電子レンジで加熱する
・耐熱容器に入れ、大さじ1の水を加え600Wで20秒加熱。
・においがやわらぎ、口当たりも良くなる。
・耐熱容器に入れ、大さじ1の水を加え600Wで20秒加熱。
・においがやわらぎ、口当たりも良くなる。
納豆を取り入れた簡単レシピ
| レシピ | 材料 | 作り方 |
|---|---|---|
| 納豆入りおかゆ | 10倍がゆ、ひきわり納豆(湯通し後) | おかゆに納豆を混ぜるだけ。粘り気が気にならず、初心者向け |
| 納豆と豆腐のペースト | 絹ごし豆腐、ひきわり納豆 | 豆腐と納豆を混ぜてペースト状にする。スプーンで食べやすい |
| 納豆じゃがいもおやき | じゃがいも、ひきわり納豆、小麦粉 | つぶしたじゃがいもに納豆を混ぜて焼く。手づかみ食べにおすすめ |
工夫すると食べやすくなるポイント
・粘りを取り除くと食べやすくなる
湯通しや加熱をすることで、 独特の粘りが軽減され、赤ちゃんも抵抗なく食べられる。
・形状を変えると興味を持ちやすい< おかゆやペースト状にするだけでなく、おやきなどにすると手づかみ食べがしやすくなる。 ・赤ちゃんの好みに合わせて調理方法を変える 食べやすい調理法を見つけることで、 徐々に納豆に慣れていくことができる。
湯通しや加熱をすることで、 独特の粘りが軽減され、赤ちゃんも抵抗なく食べられる。
・形状を変えると興味を持ちやすい< おかゆやペースト状にするだけでなく、おやきなどにすると手づかみ食べがしやすくなる。 ・赤ちゃんの好みに合わせて調理方法を変える 食べやすい調理法を見つけることで、 徐々に納豆に慣れていくことができる。
まとめ|納豆を活用して赤ちゃんの栄養をサポートしよう
納豆はたんぱく質、食物繊維、ビタミンKなどの栄養素を豊富に含み、赤ちゃんの成長にとても適した食材です。消化吸収が良く、離乳食中期(生後7〜8ヶ月頃)から取り入れやすい一方で、特有の粘りやにおいが苦手な赤ちゃんもいるため、調理方法を工夫することが大切です。納豆を使う際には、
・湯通しや加熱をして粘りやにおいを抑える
・ごはんや野菜と混ぜて食べやすくする
・手づかみしやすいおやきなどにアレンジする
といった工夫をすることで、赤ちゃんも無理なく納豆の栄養を摂取できます。また、 大豆の栄養を効率良く摂れる食品として「MASH SOY」もおすすめです。MASH SOYは、北海道産の丸大豆とおいしい水だけで作られた 無添加の大豆ペースト。納豆のように粘りやにおいがないため、 離乳食に取り入れやすく、大豆の栄養をしっかり摂取できるのが特徴です。普段の離乳食に納豆を取り入れながら、大豆の栄養をより手軽に補う方法として「MASH SOY」も活用してみてはいかがでしょうか?
・ごはんや野菜と混ぜて食べやすくする
・手づかみしやすいおやきなどにアレンジする
といった工夫をすることで、赤ちゃんも無理なく納豆の栄養を摂取できます。また、 大豆の栄養を効率良く摂れる食品として「MASH SOY」もおすすめです。MASH SOYは、北海道産の丸大豆とおいしい水だけで作られた 無添加の大豆ペースト。納豆のように粘りやにおいがないため、 離乳食に取り入れやすく、大豆の栄養をしっかり摂取できるのが特徴です。普段の離乳食に納豆を取り入れながら、大豆の栄養をより手軽に補う方法として「MASH SOY」も活用してみてはいかがでしょうか?
安心・安全な食材を取り入れながら、赤ちゃんの健やかな成長をサポートしましょう。

Riko Kobayashi
小林 理子
略歴
2014年短期大学部家政科食物栄養専攻卒業 栄養士資格取得
2014年給食委託会社入社
2015年公立小学校の栄養士へ転職
2017年管理栄養士国家資格取得/フリーランス管理栄養士へWebライター、セミナー講師、食事指導、レシピ開発等で活躍
2019年オランダへ渡航(活動休止)
2023年フューチャーフーズ株式会社に入職
2024年フリーランス管理栄養士として活動再開
活動実績
高齢者施設、学校、保育園などでの給食提供を経験し、実務を通じて専門性を磨いた後、独学で管理栄養士国家試験に合格。以降はフリーランスとして、食事指導・セミナー登壇・レシピ開発・Webライターなど幅広い分野で活躍。
オランダ滞在中に妊娠・出産を経験し、日本帰国後は 大豆製品を使ったレシピ開発 や 食品臨床試験の食事調査 を行い、現在は再びフリーランスとして活動中。
RECOMMEND